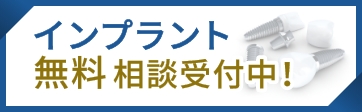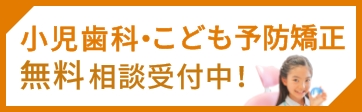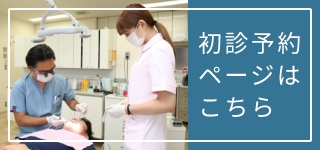骨隆起について:昔より増えた理由とは?
2025.02.12
歯科治療の現場で、「骨隆起(こつりゅうき)」を持つ患者様を以前より多く見かけるようになりました。骨隆起とは、顎の骨が口腔内で盛り上がるように突き出した状態を指します。これは病気ではなく、多くの場合、痛みや支障がないため気づかない方も多いのですが、増加の背景には現代の生活習慣や食事が関係している可能性があります。
今回は、骨隆起について詳しく解説し、その原因や対策についてご紹介します。
骨隆起とは?
骨隆起は、顎の骨が異常に成長して盛り上がる現象で、以下のような部位に見られます:
1.口蓋隆起(こうがいりゅうき)
上顎の中央部分にできる骨の盛り上がり。
2.下顎隆起(かがくりゅうき)
下顎の内側(舌側)に発生する骨の突起。
3.頬側隆起(きょうそくりゅうき)
上顎や下顎の外側(頬側)に見られる骨の突出。
これらは良性であり、健康上の大きな問題を引き起こすことは少ないですが、入れ歯や矯正装置を装着する際に支障をきたす場合があります。
昔より骨隆起が増えた理由
骨隆起が増えたように感じられる背景には、現代の生活習慣や食事が影響している可能性があります。
1.噛む回数の減少
柔らかい食事が増えた現代では、顎を十分に使う機会が減少しています。これにより顎骨の成長バランスが崩れ、骨隆起が目立つようになる可能性があります。
2.歯ぎしりや食いしばりの増加
ストレス社会の影響で、無意識に歯ぎしりや食いしばりをしている方が増加しています。これらの行動が顎骨に圧力をかけ、骨隆起の形成を促進することがあります。
3.診断技術の向上
デジタルX線や3D画像診断など、歯科医療の技術が進歩したことで、以前は気づかなかった骨隆起を発見できるようになったことも一因です。
骨隆起の対処法
骨隆起自体は治療の対象にはなりませんが、以下のような場合には対応が必要になることがあります:
1.入れ歯が当たる場合
骨隆起が入れ歯に干渉して痛みや不快感を引き起こす場合、調整や外科的な削除が必要になることがあります。
2.口内炎が繰り返しできる場合
骨隆起の周辺に口内炎ができやすい場合、日常的なケアや場合によっては手術を検討します。
3.矯正治療の妨げになる場合
矯正器具の装着や治療計画に支障がある場合は、歯科医師と相談して適切な処置を行います。
骨隆起を予防するには?
骨隆起そのものを完全に予防することは難しいですが、以下のポイントに注意することで顎骨への負担を軽減できます:
1.噛む回数を増やす
硬めの食品をよく噛んで食べることで、顎骨の成長バランスを整えます。
2.ストレスケアを行う
歯ぎしりや食いしばりを防ぐために、ストレスを適切に発散する方法を取り入れましょう。
3.定期的な歯科検診
早期発見と適切なケアが重要です。つきみ野歯科医院では、定期検診で骨隆起やその他の口腔内の変化を確認しています。
まとめ
骨隆起は良性の現象であり、多くの場合は特に問題を引き起こしません。しかし、生活習慣やストレスが関与している可能性があるため、日々のケアが大切です。つきみ野歯科医院では、骨隆起を含めたさまざまな口腔内の変化について、患者様一人ひとりに合わせたアドバイスを行っています。気になることがあれば、ぜひご相談ください!
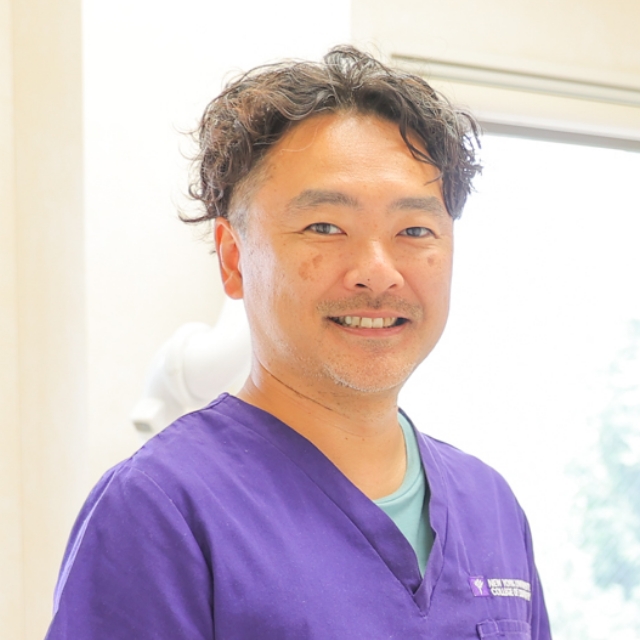
執筆者
つきみ野歯科医院
院長
2004年神奈川歯科大学歯学部 卒業。
2011年からつきみ野歯科医院に勤務して以来、地域の皆様の”歯の健康”をお守りしてまいりました。
スタッフブログでは当院の診療内容についてや、スタッフ、医院の様子なども楽しく更新していきますので、 ぜひ御覧ください。